4 高齢者に対する食育推進
高齢者については、健康寿命の延伸に向け、個々の高齢者の特性に応じて生活の質(QOL)の向上が図られるように食育を推進する必要があります。
65歳以上の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/m2)の割合は、男性で12.4%、女性で20.7%です。特に、女性の85歳以上では、27.9%が低栄養傾向となっています(図表2-3-1)。
急速な高齢化の進展により、地域の在宅高齢者等が健康・栄養状態を適切に保つための食環境整備、とりわけ、良質な配食事業を求める声が、今後ますます高まるものと予想されます。そのため、厚生労働省では、平成28(2016)年度に「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会」を開催しました。同検討会では、配食には医療・介護関連施設と住まいをできる限り切れ目なくつなぐ役割や、低栄養予防・フレイル予防に資する役割が期待されることに鑑み、地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業において望まれる栄養管理の在り方について、「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン(*1)」(以下「ガイドライン」という。)を取りまとめました。平成29(2017)年度は、配食事業者と配食利用者のそれぞれに向けた普及啓発用パンフレットを作成しました。平成30(2018)年度からは、事業者及び地方公共団体において、ガイドラインを踏まえて取り組んでいる先行事例を収集し、事業者及び地方公共団体向けの参考事例集を作成しています。令和元(2019)年度は、フレイル予防も視野に入れて策定された「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を活用し、高齢者やその家族、行政関係者等が、フレイル予防に役立てることができる普及啓発ツールを作成しました。この普及啓発ツールは、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、高齢者やその支援者向けに居宅で健康を維持するための情報等を発信するために令和2(2020)年9月に開設したウェブサイト「地域がいきいき 集まろう!通いの場」でも紹介しました。
また、農林水産省では、栄養面や噛むこと、飲み込むことなどの食機能に配慮した新しい介護食品を「スマイルケア食」として整理し、消費者それぞれの状態に応じた商品選択に寄与する表示として、「青」マーク(噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品)、「黄」マーク(噛むことに問題がある方向けの食品)、「赤」マーク(飲み込むことに問題がある方向けの食品)とする識別マークの運用を平成28(2016)年に開始しました(図表2-3-2)。平成29(2017)年度には、スマイルケア食の普及をより一層推進するための教育ツールとして、制度を分かりやすく解説したパンフレットや動画を作成しました。令和2(2020)年度には、引き続きツールを活用し、スマイルケア食の普及を図りました。さらに、地場産農林水産物等を活用した介護食品(スマイルケア食)の開発に必要な試作等の取組を支援しました。
*1 平成29(2017)年3月厚生労働省健康局策定
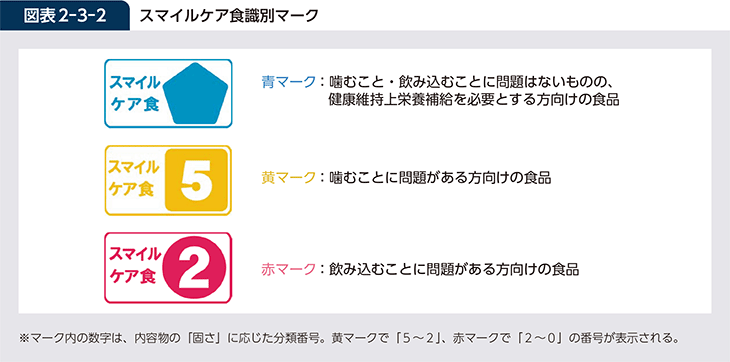
事例:「高齢者の食生活支援体制づくり」
~自然にフレイル予防になる食環境づくり~
神奈川県厚木(あつぎ)保健福祉事務所
神奈川県厚木(あつぎ)保健福祉事務所の地域食生活対策推進協議会(以下「協議会」という。)では、平成30(2018)年度から「高齢者の食生活支援体制づくり」をテーマにフレイル予防に取り組んでいます。管内の市町村と、フレイル予防の現状と課題について共有した中で、フレイル予防の必要性は認識しているが、対象者や実態が把握しにくい等の意見がありました。そこで、「プレフレイル」(フレイル予防)に着目した支援体制づくりを進めるための基礎資料とするため、令和元(2019)年11月~令和2(2020)年1月にかけて、管内7か所のスーパーマーケット等の協力を得て、買い物に来た65歳以上を対象に食事調査を行い、450名から回答を得ました。その結果を基に、食事の偏りを確認し、偏った食事内容になっている方を「プレフレイル」としてフレイル予防の取組対象者と想定しました。調査の結果、回答者の平均年齢は76歳で、450名のうち55名(12%)が「プレフレイル」であり、「プレフレイル」の方はそうでない方と比較して、「高齢者のみの世帯が多い」、「1日の食事回数が2回の方が多い」、「家庭食(家庭で調理した食事)を食べる機会が少ない」、「惣菜を食べる機会が多い」等の特徴がありました。摂取頻度の高いものは、緑黄色野菜、果物、牛乳・乳製品、摂取頻度の低いものは、肉、芋、魚介類と、本来、フレイル予防のためにたんぱく質の積極的な摂取が求められる高齢者であっても、メタボリックシンドローム予防の食事を続けていることが明らかになりました。
本調査の結果から、協議会では、フレイル予防になる食環境づくりの必要性を確認し、令和2(2020)年度は、高齢者が正しい情報を得る機会と、食物の入手環境の整備を進めることになりました。
高齢者に正しい情報を伝えるための機会として、管内の市町村から高齢者サロンを紹介してもらい、厚生労働省が作成した「食べて元気にフレイル予防」のパンフレットを用いて保健福祉事務所の管理栄養士が出前講座を行いました。また、管内の市町村で高齢者サロンの支援をしている栄養士や保健師に対して、食事内容について、メタボ対策からフレイル対策へ切り替えることの必要性を伝えました。サロンは、地域の高齢者から生活実態や正しい情報を周知する方法等の生の声を聞く良い機会となりました。
現在は、管内の市町村と連携してリーフレット(「お元気シニアの身体づくり」~食事編~)を作成しており、市町村や地域包括支援センター、自治会やスーパーマーケット等とも連携をして高齢者に周知していきます。また、今後、スーパーマーケット等とも連携し、惣菜や弁当の品揃え等、食環境の整備を併せて行う予定です。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974








